労基とは? 役割と活用事例をわかりやすく解説

「労基」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどんなことをしている機関なのか知らない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、「そもそも労基って何?」という基本的な疑問から、実際の活用事例までをわかりやすくお伝えします。
⇒ 「働く」上で必須の権利を学ぶ労務管理研修 | e-JINZAI for Business
目次
労基とは?

労基は、「労働基準監督署」の略称です。働く人たちの権利を守り、安全で健康的な職場を作るために大切な仕事をしている重要な政府の機関です。
労基は「労働基準監督署」のこと
労基は、厚生労働省の出先機関として、全国に設置されている「労働基準監督署」のことです。
その主な役割は、企業が労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法などの労働関係法令を遵守しているかを監督し、指導することです。労働者の権利保護と公正な労働環境の実現に努めており、労働条件や安全衛生の確保、労働者からの相談対応、労災保険の給付など、幅広い業務を行っています。
「労働基準監督署(労基)」と「労働基準局」との違いとは?
では、労働基準監督署と労働基準局の違いについて見ていきましょう。名前が似ているため、混同されがちですが、実際には異なる組織です。
<所在地と数>
- 労働基準局:厚生労働省内に1つだけ存在する中央機関です。
- 労働基準監督署:全国の各都道府県や地方に321署+4支署ある厚生労働省の出先機関です。
<組織構造>
労働基準局は、労働基準監督署の上位組織として、労働基準監督署や都道府県労働局を管理監督する立場にあります。
<具体的な業務内容>
労働基準局
- 労働基準法の改正や新たな労働基準の策定
- 全国的な労働条件の実態調査
- 各地の労働基準監督署の指揮・監督など
労働基準監督署
- 労働条件の監督と指導
- 労働安全衛生の確保
- 労働者からの相談・申告受付
- 労災保険の給付
- 企業への立入調査など
したがって、労働基準局は直接的な相談対応や和解あっせん、立ち入り調査などは行いません。これらの業務は主に各地の労働基準監督署が担当します。
労働基準監督署(労基)の主な役割
労働基準監督署(労基)の役割について、さらにくわしく見ていきましょう。
労働条件の監督と指導
労働基準監督署(労基)は、企業が労働関係法令を守っているか確認し、必要に応じて指導を行います。
主な業務は、労働基準法や最低賃金法の遵守状況の確認、労働時間の管理監督です。具体的には、労働契約の適正な締結や賃金の支払い、解雇規定、就業規則の届出などが含まれます。また、最低賃金法に基づき、地域別最低賃金、特定最低賃金(産業別最低賃金)が守られているかも調査します。
さらに、法定労働時間や時間外労働、年次有給休暇の管理状況も監視し、時間外・休日労働に関する労使協定である「36協定」の締結と届出を確認するのも役割のひとつです。違反があった場合は、是正勧告や指導を行い、重大な違反には刑事告発を行うことも。労働基準監督署は、法令違反の摘発だけでなく、企業の労務管理を助言し、労働環境改善を促進する役割も果たしています。
労働安全衛生の確保
労働基準監督署(労基)の重要な役割の一つは、労働者の安全と健康を守ることです。この役割には労働安全衛生法に基づく指導が含まれ、労働災害の防止と健康的な職場環境を維持するために以下のことを行います。
まず、安全衛生管理体制の整備、作業環境管理、定期健康診断やストレスチェックの実施、そして安全衛生教育が重要です。また、リスクアセスメントを実施し、職場で起こるかもしれない危険を防ぎます。
実際の職場では、機械設備の安全対策や作業方法の安全性、作業環境の衛生状態、メンタルヘルス対策、長時間労働の防止策が確認されます。問題があれば指摘され、改善のための指導を実施。重大な違反や危険がある場合は、是正勧告や使用停止命令が出されます。このように、労働基準監督署は労働者が安全で健康的に働ける環境づくりを支援しています。
労働者からの相談・申告受付
労働者の相談や申告を受け付け、労働問題の解決に取り組みます。労働条件に関する相談では、賃金未払いや残業代、有給休暇などの問題について助言し、必要に応じて使用者との調整を行います。法令違反の申告では、労働基準法違反を調査し、立ち入り検査や是正指導を実施。申告者の秘密を守り、不利益な扱いを防ぐことで、安全な労働環境を支えています。
労災保険の給付
労働基準監督署(労基)は、仕事中や通勤中の事故や病気を補償する労災保険を運用しています。労働災害が発生すると、原因や状況を詳しく調査し、事業所への立ち入りや関係者への聞き取りを行い、再発防止の指導を実施。また、労災保険給付の請求を受け付け、因果関係を慎重に審査し、適切な補償を決定します。必要に応じて専門医の意見を取り入れ、公平で適正な判断を行い、労働者を支援します。
企業における労働基準監督署対応の重要性
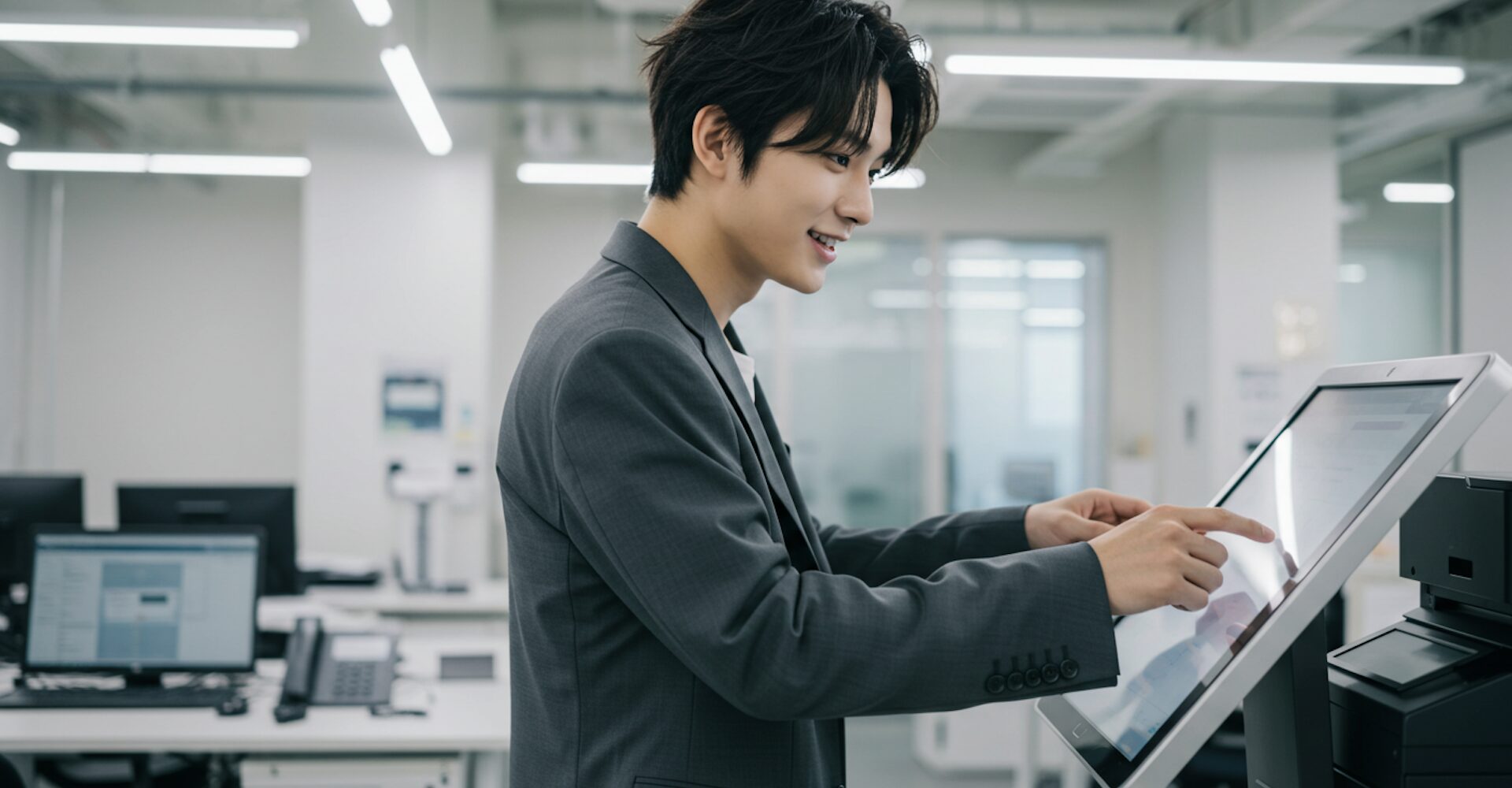
労働基準監督署への適切な対応は、企業にとって非常に重要です。以下にその理由を説明します。
コンプライアンス遵守の必要性
法令を守ることは、企業の社会的責任の基本です。労働関連法規を遵守することで、社会的信頼を得られます。一方で、違反が発覚すると、罰金や是正命令などの行政処分を受ける可能性があり、重大な場合は刑事告発され、企業の存続にも影響を及ぼしかねません。このようなリスクを防ぐためにも、定期的な自主点検と改善を行い、法令違反を未然に防ぐことが重要です。
労使関係の改善
- 労働基準監督署の指導を適切に受け入れることで、労働環境が改善され、労働者の満足度が向上します。
- 労働条件の改善は、労働者のモチベーションや生産性の向上につながります。
- 労使間のコミュニケーションが活性化し、働きやすい職場づくりに役立ちます。
- 労働争議のリスクが減少し、事業運営が安定してきます。
企業イメージへの影響
- 労働基準監督署の指導に誠実に対応する企業は、社会的評価が高まります。
- 働きやすい環境が整うと、優れた人材が集まりやすく、定着率の向上にもつながります。
- 労働問題に関する否定的な報道は、企業の評価が大きく低下する恐れがあります。
- 取引先や投資家からの信頼度にも影響し、事業機会の拡大や資金調達にも関わります。
適切な労働基準監督署対応は、単なる法令遵守にとどまらず、企業の持続的成長と社会的価値の向上に直結する重要な経営課題といえます。企業は労働基準監督署を「監視者」ではなく「パートナー」として捉え、積極的に連携していくことが望ましいでしょう。
労働基準監督署の活用事例
労働基準監督署の指導や支援を受けて、企業が労働環境を改善し、生産性が向上した事例を紹介します。
労働条件改善の事例
1. 残業時間削減の成功例
運送業の事例では、労働基準監督署の指導を受けて荷主会社と協議を行い、配送ルートの見直しにより1日当たりの便数を1便減少させ、配送業務を合理化しました。また、荷主の協力を得て荷積み作業を効率化し、自動車運転者の残業時間を短縮しました。
2.有給休暇取得率向上の取り組み
株式会社クボタでは、経営陣と労働組合が一体となって年次有給休暇の完全取得を目指す宣言を行い、それを契機に約10年間で休暇取得実績を大幅に向上させました。2022年度には、社員全体の平均で21. 3日の有給休暇取得を実現し、当初の目標を上回る成果を上げています。この成功は、経営陣が率先して有給休暇の重要性を示し、全社的な取り組みとして推進したことによるものです。
労働安全衛生向上の事例
1.職場環境改善による労働災害減少
ある製造業の事業者では、家内労働者に委託する作業について、安全性や身体への影響について確認したうえで発注するようにしました。また、定期的に「内職者会議」を開催し、そこで得た情報を安全衛生活動に反映させています。
2.メンタルヘルス対策の成功例
労働基準監督署は、企業に対してストレスチェックの実施と結果に基づく措置を指導しています。また、メンタルヘルス対策として相談窓口の設置と周知を推奨しています
生産性向上の事例
介護業界の事例では、服薬ボックスの導入や作業分析を行い、職員の役割や業務分担、手順を見直すことで、業務の効率化を実現し、生産性を33%向上させました。
「とりそば下地橋」は、業務効率化により賃金アップを実現した事例です。この飲食店は2023年1月に従業員すべての時給を90円引き上げました。その背景には業務改善助成金を活用した取り組みがあります。新設備の導入により生産性を向上させ、従業員のモチベーション向上や店舗の活性化にも貢献。さらに、周辺の他社よりも高い賃金を設定することで、人材確保と雇用の安定を実現しました。
最近の労働基準監督署の取り組み
近年、労働基準監督署は変化する労働環境に対応するため、さまざまな取り組みを行っています。以下では、特に注目される最近の活動についてご紹介します。
働き方改革関連法への対応
労働基準監督署は、2024年5月に公布された育児・介護休業法改正法の施行に向けて、企業への指導を強化しています。主な取り組みには以下が含まれます。
- 子の看護休暇の見直しに関する指導
- 所定外労働(残業)の免除対象拡大についての周知
- 育児中のテレワーク導入推進の支援
- 企業に対する育児休業取得状況の公表義務拡大への対応
新型コロナウイルス感染症対策
労働基準監督署は、職場での新型コロナウイルス感染拡大を防止するために以下の取り組みを行っています。
- 新型コロナ感染症拡大防止チェックリストの改訂と周知
- 事業者に対する集団感染の早期封じ込めと基本的な感染予防の徹底の指導
- 職場内外での感染防止行動の徹底に関する正しい知識の普及
テレワーク時代の労務管理指導
テレワークの急速な普及に伴い、労働基準監督署は以下の点に注力して労務管理指導を行っています。
- テレワーク中の労働時間管理の徹底指導
- テレワークにおける労務管理のガイドラインの活用促進
- 在宅勤務時の超過労働防止に関する指導
- テレワーク環境下での労働安全衛生管理の指導
これらの取り組みを通じて、労働基準監督署は変化する労働環境に対応し、労働者の権利保護と健全な労働環境の実現を目指しています。
まとめ
労働基準監督署(労基)は、私たちの働く環境を守るために欠かせない存在です。これからも、労基は働き方改革や社会の変化に対応しながら、より良い労働環境を目指して取り組んでいくことが期待されています。企業も、自主的に改善活動を進めることで、持続可能な成長と労働者の幸せを追求していくことが大切です。
働く側の労務管理研修
労務管理は企業側の責務ですが、働く(労働者)側の私たちにどのような権利や規定があるかを知っている人は少ないのではないでしょうか。 e-JINZAI for Businessの労務管理研修では、 働く側が知っておきたい労務管理の知識をご紹介します。
2週間無料お試しはこちら


